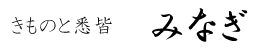| 算木とは、古代日本に中国より伝来した棒状の計算器具のことである。算盤(さんばん)と呼ばれる補助器具上で、簡単な四則計算は勿論、平方根を求めることもできた。江戸時代初期に中国から伝来した『天元術』を用いることによって、高次方程式の解を求めることができた。西洋数学が普及する明治時代まで、日本では簡単な計算はソロバンを、そして天元術など難しい計算には算木を用いていた。 使用家は、星合、今村、寒河江、加藤、滝川氏など。 |
|
|
参考資料 講談社「家紋と家系辞典」他 |
|
|
|
|
|
|
|
丸に一つ算木 |
丸に二つ算木 |
丸に算木 |
算木 |
石持ち地抜き算木 |
|
|
|
|
|
|
|
丸に縦算木 |
丸に |
丸に縦横算木 |
丸に十の字算木 |
組み合わせ枡に |
|
|
|
|
|
|
|
丸に木の字
|
六つ組木 |
くの字木菱筋違 |
中輪に |
三つ組み筋違 |
|
|
|
|
|
|
|
四つ組み違い木
|
組み違い木 |
丹羽違い木 |
丸に中陰十の算木 |
変わり組み木
|
|
|
||||
|
隅切角にゆり三木 |
||||
メインメニュー
着物について
和辞典
Copyright © 2024 きものと悉皆みなぎ - All Rights Reserved. Designed by Devpri