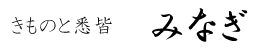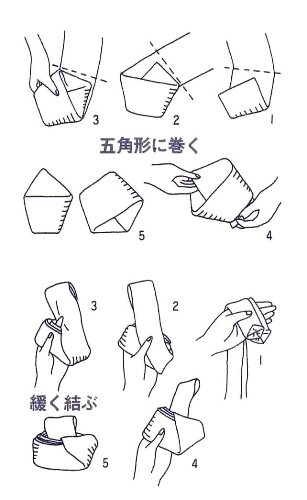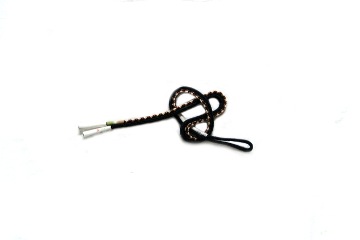| |
| 7. 肌着は洗濯へ |
- 長襦袢、裾よけは直接肌に触れるものですから、着るたびに、すぐに洗濯します。そのため、着心地がよく、洗濯しやすい素材がよいでしょう。木綿やキュプラなどは、静電気が起きにくいという点でもお勧めです。
|
| |
| 8. 長襦袢と半衿 |
- 長襦袢は、湿気が抜けたら半衿を外してからたたんでしまいます。外した半衿は、洗濯してからしまいます。ただし、ほとんど汚れていないようなら、長襦袢に付けたまま、ベンジンで簡単に手入れして、もう一度くらい着てもよいでしょう。無地の化繊の半衿は簡単に洗えますが、それ以外の半衿の取り扱いには注意して、商品の表示の指示に従って手入れします。
|
| |
| 9. 足袋は隅まできれいに |
- 足袋も、すぐに洗濯します。手洗いか、洗濯機ならネットに入れて弱水流で洗います。干すときは、布目や縫い目に沿ってシワを伸ばしておきます。足に合った足袋なら、基本的にアイロンを掛ける必要はありません。底の縫い目などが特に汚れていたら、歯ブラシに洗剤をつけて円を書くように洗います。
|
| 10. 草履の埃を落とす |
- 脱いだ後は、底の湿気を取るために立てかけて陰干しします。佐賀錦など布地の草履は、ガーゼなどの柔らかい布で、布目に沿って軽く叩くように埃を取ります。エナメルは、やはり布で拭き、汚れていたらエナメル用のクリーナーを使います。草履も湿気に弱いので、風通しのよいところにしまいます。特に裂地のものは、帯と同様に気をつけて保管しましょう。
|
| 番外編 アイロンを当てるときは |
 |
目立つシワが残ったときは、着物の裏から当て布をしてアイロンを掛けます。あて布には晒しなどの白い木綿で糊気のないものを使い、アイロンは、こすらず、上からさっと重みを掛けるように当てます。
スチームアイロンの蒸気は、きものが収縮する恐れがあるので使用しないほうがよいでしょう。シワが取れにくいときは、当て布に霧吹きで軽く霧を吹きます。縫い目の周りは生地の重なりの跡がつきやすいので注意するほか、刺繍や箔のところは避けて掛けます。ただし、強いシワや高価なものは専門家に任せましょう。
|
|
|
| |
|
この記事は「婦人画報社」2004年版を引用しています
|