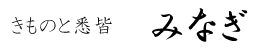幾何・割付文様
麻の葉 (あさのは)
| 麻の葉文様とは、正六角形を基礎にした文様で形が大麻の葉に似ているのでこの名があり、きものや長襦袢のほか絣織物にもあり、また麻が丈夫で成長が早いことから、子どもの産着として現代でも用いられています。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
麻の葉 |
麻の葉 |
麻の葉に向い鶴 |
麻の葉くずし |
麻の葉くずし |
|
|
|
|
||
|
麻の葉くずし |
麻割に雲 |
捻れ麻の葉 |
||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています |
網代・檜垣 (あじろ・ひがき)
|
檜の薄板や竹、葦などをうすくして編んだものを網代といいます。また檜垣は檜板で編んだ垣根のことをいいます。
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
網代・檜垣 |
網代・檜垣 |
檜垣 |
檜垣 |
檜垣 |
|
|
|
|
|
|
|
紋入り檜垣 |
網代 |
網代に梅 |
檜垣に蝶 |
|
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
網目 (あみめ)
| 漁業用の網の目の文様で、リズム感のある曲線が美しく江戸時代に愛用されたが、早くは縄文時代の土器にも見受けられる。海老や蛸や魚をあしらって大漁紋として浴衣や手拭などにも染められてた。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
網目 |
網目 |
網目 |
紋入り変わり網目 |
|
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
渦巻 (うずまき)
| 幾重にも巻いた曲線文様。古くから世界各地で使われ、現代感覚の染織にも多く見られます。小紋にも渦巻き模様があり、江戸時代の歌舞伎役者・市村亀蔵が着た亀蔵小紋は、そのひとつです。くっきりとした味がしゃれ着や浴衣に好まれます。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
渦巻き |
渦巻き |
渦 |
勾玉(まがたま) |
渦巻千鳥 |
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
籠目 (かごめ)
| 竹で編んだ籠の網目をそのまま文様化したもので、幾何学文様のひとつです。単独で使われることもありますが、多くは花などを添えて用いられています。魔除けの意味があります。 | ||||
|
|
|
|||
|
籠目 |
籠目 |
|||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
亀甲 (きっこう)
| 亀甲文様とは正六角形の繋ぎ文様で亀の甲羅に見立ててこの名がつけられました。平安時代以来、公家の邸宅の調度・服装・輿車(こしぐるま)などの装飾に用いられた独自の様式をもつ文様の総称です。古典文様として現在まで受け継がれていて吉祥文様の一つとされます。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
星亀甲 |
重ね亀甲 |
重ね亀甲 |
重ね亀甲に七つ星 |
花亀甲 |
|
|
|
|
|
|
|
花亀甲 |
菊入重ね亀甲 |
十入り亀甲 |
変わり亀甲 |
角(つの)亀甲 |
|
|
|
|
|
|
|
亀甲くずし |
毘沙門亀甲 |
毘沙門亀甲(組亀甲) |
向い亀甲 |
花入り破れ亀甲に笹蔓文 |
|
|
||||
|
七星入り破れ重ね亀甲と松葉 |
||||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
行儀 (ぎょうぎ)
| 行儀文様とは点の並びが斜めに交差する柄のことをいいます。規則的に毅然と並んでいるところから行儀作法、礼を尽くすの意味があります。「極行儀」は1寸四方に900余の穴、「似たり行儀」は1寸四方に700~800余の穴のものをいいます。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
極行儀 |
似たり行儀 |
行儀 |
大小霰行儀 |
|
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
格子 (こうし)
| 格子文様は縞文様のひとつです。縞文様の中で、縦横の筋が碁盤の目状に交差した文様で四角形の連続したものを格子といいます。四角形の中にいろいろな文様を組み込んだものが多くあります。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
米格子 |
米格子 |
円入り格子 |
文入り格子 |
変わり格子 |
|
|
|
|
|
|
|
変わり格子 |
花格子 |
三筋格子 |
障子格子 |
二本格子 |
|
|
|
|
||
|
巴格子に花 |
文入り変わり格子 |
文入り変わり格子 |
||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
小紋尽くし (こもんづくし)
| 裂取り文様ともいい、パッチワーク風に異なった文様で構成したものをいいます。 | ||||
|
寄せ裂 |
寄せ裂 |
寄せ裂 |
寄せ裂 |
地紙取り |
|
松皮菱取り |
霞取り |
繋ぎ文様 |
地紙尽くし |
小紋縞 |
|
|
||||
|
遠山取り |
||||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
鮫 (さめ)
| 鮫文様とは鮫の皮のような半円を重ねた文様のことをいいます。この鮫小紋は小紋がらの中で最も古い文様のひとつで、肩衣や裃の文様として使われました。江戸時代に武士の間では、礼装であった裃の文様を大名ごとに独占しましたが、紀州家はこの鮫小紋を占有しました。これを総称して「定め小紋」と呼ばれました。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
極鮫 |
似たり鮫 |
鮫 |
鮫 |
|
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
紗綾形 (さやがた)
| 紗綾形文様とは卍を斜めに崩して連続文様にしたものをいいます。中国明の時代に輸入された紗綾という絹織物にこの模様が多く使われていたためにこの名称になったとされています。桃山、江戸時代は地文がほとんど紗綾形で、綸子に紗綾形として非常に多く使われていました。「不断長久」を意味する吉祥文様であることから、昔は女性の慶事礼装用の白襟には紗綾形が使われるものと決まっていたそうです。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
紗綾形・卍くづし |
紗綾形 |
紗綾形 |
紗綾形 |
卍格子 |
|
|
|
|
|
|
|
七宝変わり紗綾形 |
エ字繋ぎ |
変わり紗綾形 |
変わり紗綾形 |
|
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
七宝 (しっぽう)
| 七宝の円形は円満を表し、吉祥文様の一つです。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
七宝 |
七宝 |
七宝 |
極七宝 |
菊入変わり七宝 |
|
|
|
|
|
|
|
霰七宝 |
六方輪違い |
花入り七宝 |
花七宝 |
|
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
縞 (しま)
| 江戸時代以前は縞柄といえば筋と呼ばれる横縞がほとんどでしたが、南蛮貿易によって縦縞の木綿が入ってくると、縦縞は「縞物」と呼ばれて、大変流行しました。当時の町人の間でもてはやされ、縞の種類も様々に考案されました。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
極毛万 |
毛万 |
三筋立 |
一・三筋 |
均通し(金通し) |
|
|
|
|
|
|
|
子持ち縞 |
二・三・四筋 |
薩摩縞 |
滝縞 |
よろけ縞 |
|
|
|
|
|
|
|
竹縞 |
変わり養老(よろけ)筋 |
竹縞分銅繋ぎ |
竹縞 |
竹縞 |
|
|
|
|
|
|
|
木賊(とくさ)縞 |
柳縞 |
よろけ柳縞 |
刺子縞 |
矢鱈縞 |
|
|
|
|
|
|
|
鎖縞 |
縄目縞 |
縄目縞 |
茣蓙(ござ)目縞 |
手綱 |
|
|
|
|
|
|
|
霞縞 |
霰のよろけ縞 |
輪繋ぎ |
蝶縞 |
小矢羽根 |
|
|
||||
|
矢絣 |
||||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
蜀江 (しょっこう)
| 中国から伝来した蜀江錦の織り出されている文様を言います。その特徴は、八角形と四角形がつながったようになり、その中にいろいろな文様が入ります。現代では忠実な蜀江写しもありますが、中の文様を現代風にしたものなどもあり、帯地にもみられます。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
花蜀江 |
花蜀江 |
花蜀江 |
花蜀江 |
花蜀江 |
|
|
|
|
||
|
菊蜀江 |
雲に雨龍入り蜀江 |
紋入り蜀江 |
||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
青海波 (せいがいは)
| 波文様の1つで、同心円を互い違いに重ねた文様です。起源は古く、中国では地図上で海を表すものに用い、日本では陶器・蒔絵・能装束・小袖などに見られます。現在では、吉祥文様として礼装用の地紋や染織品の柄として幅広く用いられています。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
青海波 |
青海波 |
青海波 |
変わり青海波 |
菱青海波 |
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
立湧 (たてわく)
| たちわきともいい、有職文様の一つで、波型のラインが2本向き合って並んだ文様です。ふくらんだ部分に、菊・桐・雲などの文様を詰めたものもあり、雲立涌、花立涌、波立涌などと呼び、奈良時代から現在まで用いられています。染織品によく使われています。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
立湧 |
花立湧 |
破れ花立湧に唐草 |
花立湧に千鳥 |
雲立湧に蔦 |
|
|
|
|||
|
千鳥立湧 |
雨龍立湧 |
|||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
通し (とおし)
| 通し文様とは柄の縦横が直角に交差し等間隔に並べられた点模様のことをいいます。筋を通すという意みがあり、「錐彫り」という技法で作られています。小紋柄では最も古い技法で、針先が半円形になった小刀で回転しながら細かな穴を彫り、一番細かいものは一寸四方の中に900~1000、もの穴を彫り上げます。「極通し」は1寸四方に900余の穴、「似たり通し」は1寸四方に700~800余の穴のものをいいます。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
極通し |
似たり通し |
通し |
角通し |
|
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
菱 (ひし)
| 菱文とは菱の実のような形の文様のことをいいます。菱文が隣接して沢山並ぶのを繁菱、間隔を置いて並ぶのを遠菱といいい、また縦長の菱文を立菱といって区別する。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
幸菱 |
花菱 |
武田菱 |
二五菱 |
九曜菱 |
|
|
|
|
|
|
|
星入り菱格子 |
菱に一引き |
菱格子に三ツ星 |
花入り菱格子 |
花入り菱格子 |
|
|
|
|
|
|
|
花入り菱格子 |
竹節入り菱格子 |
花入り斜格子 |
二の地入り菱格子 |
御召十 |
|
|
|
|
|
|
|
業平菱 |
菱格子 |
猫足文 |
変わり鹿の子 |
剣菱 |
|
|
|
|
|
|
|
菊菱 |
米地入り花の菱格子 |
菊入菱格子 |
麻の葉入り菱格子 |
入子菱 |
|
|
||||
|
文入り斜格子 |
||||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
分銅繋ぎ (ぶんどうつなぎ)
| 小紋柄などに見られる菱文様の一種で、うねりのある曲線でひし形をつないでいます。宝尽しの一つである文銅をつないだように見えることからこの名があり、分銅繋ぎとも呼ばれます。地模様をして草花と組み合わせたり、皮脂の中に文様を詰めたりして使われます。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
分銅繋ぎ |
分銅繋ぎ |
竹の分銅繋ぎ |
重ね分銅繋ぎ |
紋入り変わり分銅繋ぎ |
|
|
|
|
||
|
松葉分銅繋ぎ |
花の分銅繋ぎ |
霰分銅繋ぎ |
||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
星 (ほし)
| 小紋形の場合点を星ともいいます。その神秘性から信仰の対象伴っています。光り輝くもの「日、月・星」を総称して「曜」といいます。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
九曜繋ぎ |
菊に九曜繋ぎ |
井筒七つ星 |
賽の目(さいのめ) |
三ツ星 |
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
松皮菱 (まつかわびし)
| 菱形の上下に小さな菱形を重ねたような幾何学文様で、松の木の表皮に似ているところからこの名がつきました。平安時代末期から鎌倉時代にかけての絵巻物にも多数見られ、桃山時代の辻が花染にも多く用いられています。この形を平面でいくつかに区切って文様付けした松皮菱取りも多用されています。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
松皮菱 |
松皮菱 |
角松皮菱 |
鉄砲松皮菱 |
霰松皮菱 |
|
|
|
|
|
|
|
花入り松皮菱 |
松皮菱入り菱格子 |
重ね松皮菱 |
九曜入り変り松皮菱 |
片松皮 |
|
|
||||
|
三階菱 |
||||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
山道 (やまみち)
| 山の斜面を登るようにジグザグの線で表わされた文様で、山形が3つ以上連なったものをいいます。能装束や小袖の地紋にも使われ、横段の柄に対し縦柄になり、裾模様などに用いられています。単独以外に他の文様をあしらって用いられることもあります。 | ||||
|
|
|
|
||
|
変わり山路霰に桜 |
山道(山路) |
山道に桜 |
||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
雪輪 (ゆきわ)
| 雪の文様の1つで、雪の結晶に見られる美しい六角形の輪郭を円形に描いた文様です。桃山時代の能装束などによく見られ、「雪花図説」の結晶図は有名です。雪輪の中に他の文様を描いたり、文様の区切りに用いたりもします。振袖・留袖・小紋・帯など幅広く用いられています。 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
雪輪 |
雪花 |
雪花 |
雪花 |
重ね雪輪に扇散し |
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |
割付柄 (わりつけがら)
| 文様構成上の1つの方法です。1個の文様を四方に連続させて、規則的な配置を繰り返し、一定の区画内(布の面積)に割り付ける方法で、模様づけの総称でもあります。代表的なものに麻の葉・亀甲・青海波・市松などがあります。名称がないものも多くあります | ||||
|
|
|
|
|
|
|
梨割 |
胡麻・鍋島 |
中星又麻 |
紋入り斜格子 |
鱗 |
|
|
|
|
|
|
|
鱗 |
市松 |
石畳 |
宇治川 |
手綱取一文字 |
|
|
|
|
|
|
|
三くずし |
屋根 |
変わり木賊 |
花勝見 |
浮線綾 |
|
|
|
|
|
|
|
小葵文 |
庵木瓜 |
捩れ麻の葉 |
からせみ |
割山椒 |
|
|
|
|
|
|
|
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
|
|
|
|
|
|
|
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
|
|
|
|
|
|
|
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
|
|
|
|
|
|
|
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
|
|
|
|
||
|
割付文様 |
割付文様 |
割付文様 |
||
|
「日本の文様染の型紙」 熊谷博人/編 クレオ/出版 2006.10 より引用しています。 |