6月(水無月)
| ■ |
JUNE |
≪水無月≫ |
命を潤す長雨の季節 |
|
|
6 月 |
参考・引用 : 自由国民社「現代用語の基礎知識」より引用しています
| ◆ 芒種(ぼうしゅ) | |
|
芒種(ぼうしゅ)は、二十四節気の1つ。または、この日から夏至までの期間。新暦6月6日ごろ。冬至から167日目で6月7日ごろ。 |
|
| ◆ 夏至(げし) | |
|
一年で昼の長さが最も長くなる日。二十四節気のひとつで新暦6月21日頃。冬至から182日目で6月22日ごろ。冬至(12月22日頃)に比べると、昼間の時間差は4時間50分もあります。(夏至: 昼14時間35分/夜9時間25分 冬至:昼9時間45分/夜14時間15分‥いずれも 東京の場合) 暦の上では夏にあたりますが、実際には梅雨でうっとうしい時期です。また、日本と 違って暗く長い冬が続く北欧では、この日は特別の喜びを持って迎えられ、各国で 盛大に夏至祭が行われます。 『夏至今日と思ひつつ書を閉ぢにけり』(高浜虚子) |
|
| ◆ 入梅(にゅうばい) | |
|
入梅を意味する雑節の一つ。芒種から5日目、立春から数えて135日目に当る6月11日頃の時期をいいます。新暦6月11日頃。暦の上では芒種(新暦6月6日頃)の後の最初の壬(みずのえ)の日で、梅雨明けは、二十四節気の一つである小暑(新暦7月7日頃)の後の最初の壬の日とされる。 |
|
| ◆ 夏越の祓(なごしのはらえ) | |
|
六月の最終日。一年の上半期の最後の日。六月の晦日の神事。夏越の祓はまた、水無月の祓(みなづきのはらえ)とも呼ばれ、昔は、名越の祓と書いた。大晦日の「年越しの祓え」とともに罪や穢れを祓う「大祓え」と呼ばれる風習。 |
|
| ◆ 貴船祭(きふねまつり) | |
|
毎年6月1日に行われる京都・貴船神社の例祭。貴船神社は水の神を祭り、水に浮かべて文字を読み取るおみくじや縁結び、丑の刻参りの伝説など、古くから神秘的な神社として知られている。祭りでは五穀豊穣と無病息災を祈って「乙女舞」が奉納され、本宮から貴船川上流の奥宮まで神輿が出る。 |
|
| ◆ 時の記念日(ときのきねんび) | |
|
6月10日。『日本書紀』には671年の旧暦4月25日に宮中で漏刻(水時計)が設置されたことが記されており、これが日本における時報の起源とされる。この日は新暦6月10日にあたり、1920年(大正9年)から「時の記念日」と定められた。時の祖神とされる天智天皇を祀る滋賀県大津市の近江神宮では、毎年6月10日に漏刻祭(ろうこくさい)が行なわれる。また、日本標準時の基準となる子午線が通る兵庫県明石市では、時の記念日にちなんでさまざまな行事が行われている・ |
|
| ◆ 父の日(ちちのひ) | |
|
普段存在のありがたみを忘れられがちなお父さんに感謝を表す日。6月の第3日曜日。1909年にアメリカ・ワシントン州スポケーンのソノラ・スマート・ドッドが、彼女を男手1つで自分を育ててくれた父を讃えて、教会の牧師にお願いして父の誕生月である6月に礼拝をしてもらったことがきっかけと言われている。 |
|
| ◆ 川明(かわあき) | ||
|
鮎釣が解禁されること。夏の季語。5月末から7月、各河川を管理する漁業協同組合が設定した竿釣の
解禁日には、特に友釣りの愛好者が一斉に繰り出す。関東地方では6月1日に川明を迎えるところが多い。川に入るときには、所定の店で入漁券(入川券、遊魚証などとも呼ぶ)を事前に購入し、携帯する。太公望たちが待ち望む、夏の一日。 |
||
| ◆ 新生姜(しんしょうが) | ||
|
薬味として一年中味わえる生姜の中で、根がまだ固くなっていない6月から8月に出回る瑞々しい生姜
を新生姜という。全体に白い部分が多く、その白い部分と紅い部分の色彩がはっきりとしたもの、しっとりとしたものがよいとされる。甘い味が特徴。新陳代謝を高め、発汗を促進し、胃腸を整える作用のほか、殺菌作用もあり、古くから薬用に用いられてきた食品。生姜は秋の季語となっている。 |
||
| ◆ 青梅(あおうめ) | ||
|
梅は立春の頃に花を咲かせることから春の季語となっているが、その実は初夏に実るため、青梅、梅の実、梅酒、梅干などは夏の季語になっている。梅雨前に取れた青梅で梅肉エキス、その後、梅酒や梅ジュース、梅雨の雨を2、3回あてた梅で梅干し、そして梅煮作りと、梅の味わい方はさまざま。梅に含まれるクエン酸は血液をきれいにし、疲労回復や胃腸の働きを整えるなどの効果がある。
|
||
| ◆ 薪能(たきぎのう) | ||
|
薪能(たきぎのう)は、主として夏場の夜間、能楽堂、もしくは野外に臨時に設置された能舞台の周囲にかがり火を焚いて、その中で特に選ばれた演目を演じる能。「薪の宴の能」の意。起源は平安時代中期にまで遡り、奈良の興福寺で催されたものが最初だという。興福寺では、現在5月の11日、12日に薪能が行われている。ただし興福寺では薪御能(たきぎおのう)と呼ぶ。また、薪御能の源流はあくまで神事・仏事の神聖な儀式であり、野外で薪を燃やせば薪能になるのではないとしている。 |
 |
|
| ◆ 水芭蕉(みずばしょう) | ||
|
サトイモ科の多年草で、夏の季語。湿地に自生し発芽直後の葉間中央から純白の仏炎苞
(ぶつえんほう)と呼ばれる苞を開く。これが花に見えるが仏炎苞は葉の変形したものである。仏炎苞の中央にある円柱状の部分が小さな花が多数集まった花序(かじょ)である。開花時期は低地では4月から5月、高地では融雪後の5月-7月にかけて。 |
||
| ◆ 梔子(くちなし) | ||
|
アカネ科クチナシ属の常緑低木。5月から7月にかけて白い花をつけ、強い香を放つ。野生では森林の
低木として出現するが、園芸用として栽培されることも多い。「梔子の花」は夏の、「梔子の実」は秋の季語。10月から11月頃赤黄色の実をつけ、染料や薬用として用いられるなど様々な利用がある。 |
||
| ◆ 泰山木(たいさんぼく) | ||
|
モクレン科の常緑高木。北アメリカ原産。葉は長楕円形で大きく、革質で表面は濃緑色、裏面には
さび色の密毛がある。5月から7月に手のひらほどもある大輪の白い花をつけ、強い芳香を放つ。「泰山木僕の花」は夏の季語。背が高いものは20m以上にもなり、その姿が立派なので中国の名山である泰山の名が付いたといわれている。 |
||
| ◆ 衣更(ころもがえ) | |
|
衣替えは季節に応じて衣服を着替えることをいい、季節の変化がはっきりしている日本特有の習慣で、古くからの宮中行事でした。現在では、気候に合わせて何を着ても自由と言う合理的な風潮になっていますが、和服では今もこの習慣が守られていて、その日の気候にかかわらず、6月1日からは「単(ひとえ)」、10月1日からは「袷(あわせ)」とされています。 |
|
| ◆ 夏のきもの(なつのきもの) | |
|
6月から9月のきものは裏地をつけず、一枚仕立てにした「単」を着ます。さらに、盛夏には「単衣の時期」と「薄物の時期」があります。単衣の時期、すなわち6月と9月は、透けない単衣や紗に紗や絽をあわせた「紗あわせ」を着ます。6月は桔梗の紫や、アザミの赤、藍、寒色系の濃い色や白っぽい色、9月はもう少し黄味を帯びた色合いで、柄は露草や百合、9月になると秋草や虫かごなど涼しげな風物を、帯は紗や絽の袋帯、絽綴(9月)が最適です。 |
|
【準備中】
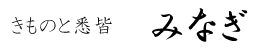







 花言葉は
花言葉は