4月(卯月)
| ■ |
APRIL |
≪卯月≫ |
穏やかな陽光を浴びて |
|
|
4 月 |
参考・引用 : 自由国民社「現代用語の基礎知識」より引用しています
| ◆ 清明(せいめい) | |
|
「清浄明潔」の略で、春の穏やかな陽光を受けて自然の息吹が清々しい様を意味する節気の一つ。新暦4月5日頃。春分後15日目にあたり、農耕の季節の幕開けの時期とされる。古来中国では清明節と呼ばれ、春を迎えて先祖の墓参をしたり、郊外に出かけて宴を催す風習があった。現在でも中国や沖縄地方ではこの時期に墓参をする習慣が残っている。 |
|
| ◆ 穀雨(こくう) | |
|
穀物を育てるあめを意味する節気。新暦4月20日頃。この時期は、前年の秋に蒔いた麦の成長を促す春の雨が降り、清明のころに蒔いた籾が稲に育っていく頃で、農耕にかかわる人々にとっ手恵みの雨となる。この時期に長引く雨を菜種梅雨(なたねづゆ)という。穀雨の終わりごろに八十八夜がある。 |
|
| ◆ 春の土用(はるのどよう) | |
|
立夏までの約18日間にあたる雑節の一つ。春の土用の入りは新暦4月17日頃。土用とは「土旺用事」の略で、陰陽五行説による季節の割り振りで四季に配当(冬:水、春:木、夏:火、秋:金)されなかった「土」の支配する時期として各季節の末18日ないし19日間を指すもの。季節の変わり目にあたる。現在は夏土用のみを土用と言うことが多い。 |
|
| ◆ 潅仏会/花祭り(かんぶつえ/はなまつり) | ||
|
灌仏会(かんぶつえ)は、釈迦の誕生を祝う仏教行事である。日本では原則として毎年4月8日に行われる。
釈迦(ゴータマ・シッダッタ)が旧暦の4月8日に生まれたという伝承に基づく。降誕会(ごうたんえ)、仏生会(ぶっしょうえ)、浴仏会(よくぶつえ)、龍華会(りゅうげえ)、花会式(はなえしき)、桜が満開の時期なので花祭(はなまつり)の別名もある。関西では5月8日に行うところもある。釈迦誕生の際には天から龍がやってきて甘露の雨を注いだ。それにならって日本では花で飾った花御堂をつくり、その中の水盤に誕生仏をおいて、参拝客や僧侶が柄杓で甘茶をかけて祝う。この甘茶を飲むと厄除けになるという言い伝えもあり、持ち帰って家族みんなで飲む習慣もある。 |
||
| ◆ 春眠(しゅんみん) | ||
|
《孟浩然「春暁」から》 春眠不覺曉 處處聞啼鳥 夜来風雨聲 花落知多少 春ならば、日中のうたた寝を戒められても、この一節を唱えてやり過ごせそうなきがする。 |
||
| ◆ 桜漬け(さくらづけ) | ||
|
4月中旬、満開前の八重桜の花やつぼみを塩と梅酢で漬けたもの。茶碗に入れて熱湯を注ぐと、花びらが開
いて香が立つ。春の季語。見合いや婚礼などの祝いの席では、「茶を濁す」ことを忌み嫌うことからお茶の代わりにこの桜湯をいただく。お茶漬けにのせる、炊き立てのご飯に混ぜる、焼酎のお湯割りに入れる、アンパンにのせる、和菓子やアイスクリームに入れるなど用途は広い。神奈川県秦野市では江戸時代末期から生産されており、現在も特産品の一つ。大根などを梅酢で着けたものを「桜漬け」という地方もあるため、それと区別して「桜花漬け」というばあいもある。 |
||
| ◆ 初鰹(はつがつお) | |||
|
春から初夏にかけて、南方の海から日本近海の太平洋を黒潮に乗って北上する鰹を「初鰹」または「上り鰹」という。江戸時代には駿河湾、相模湾あたりの沖合いで獲れ、珍重された。あっさりとした上品な味が特徴。江戸時代、鰹の刺身は皮付きのものをからし醤油で食べるのが習慣だったが、今は「たたき」にして生姜で食べるのが一般的。春の魚の代表格。 |
|||
| ◆ 春のお菓子(はるのおかし) | |||
|
春のお彼岸にお供えされる「牡丹餅」、一方、秋のお彼岸の「おはぎ」。これは、春は牡丹(ぼたん)が咲くから「牡丹餅」、秋は萩の小花にちなんで「おはぎ」と呼ぶという説があります。季節の花にちなんだ和菓子は多く、中でも花盛りの春は、和菓子も華やかなものが勢揃いします。
|
|||
|
◆ 春の山菜(はるのさんさい) |
|||
|
山菜は「その日に山に帰る」といわれるように鮮度が落ちやすいもの。処理は摘んだその日に行い、その日に食べるか、乾燥させたり塩漬けにして保存食にします。保存した山菜は季節のお祭り、慶事や法事などに用いられる。
|
|||
| ◆ 桜(さくら) | |||
|
春に白色や淡紅色から濃紅色の花を咲かせ、日本人に古くから親しまれている。また、果実を食用とするほか、花や葉の塩漬けも食品などに利用され、海外においては一般的に果樹としての役割のほうが重視された。環境がよければ寿命は非常に長く、老木として著名な日本五大桜の内神代桜は樹齢が1800年を超えているとされる。
|
|||
| ◆ 花冷え(はなびえ) | |
|
桜の花が咲く頃に訪れる一時的な寒さ、一種の「寒の戻り」のこと。春の季語。4月は不安定な天候が続き、「春に3日の晴れなし」ともいわれる時季でもある。東北地方の一部の地域では、花冷えのことを、桜の開花の便りが聞かれるにもかかわらず、炬燵やストーブをしまいきれずにいる状態から「花炬燵」ともいう。この花冷えで、時には晩霜(おそじも)が降り、農作物などにも多大な損害をもたらすことも少なくない。 |
|
【準備中】
【準備中】
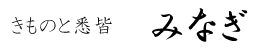








 花言葉は
花言葉は