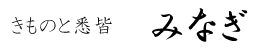12月(師走)
| ■ |
DECEMBER |
≪師走≫ |
慌ただしくなる年の瀬 |
 |
|
12 月 |
参考・引用 : 自由国民社「現代用語の基礎知識」より引用しています
| ◆ 大雪(たいせつ) | |
|
寒さが次第に厳しくなり、雪が降り積もる頃の節気。新暦12月7日頃。熊が冬眠をはじめ、鮭が川を遡上してくる時期。師走に入り何かと気ぜわしくなり、町はクリスマスの装いに包まれる。 |
|
| ◆ 冬至(とうじ) | |
|
一年で夜の時間が最も長くなる日。二十四節気の一つで新暦12月22日頃。この日を境に昼の時間が長くなり春に向かうことから「一陽来復(いちようらいふく)」ともいう。その様子を古の人は、米の粒一つずつ、畳の目一つずつ日が長くなると表現した。冬至にカボチャを食べ、柚湯に浸かると風邪をひかないといういいつたえがあり、その風習はいまなお各地に残っている。古来中国ではこの日に小豆粥を食べ、疫病を祓い無病息災を祈る行事が行われていた。 |
|
| ◆ 正月事始(しょうがつことはじめ) | |
|
旧暦12月13日に行われていた、正月を迎えるための準備をする行事。現在の暦では12月8日、あるいは13日に行われることが多い。かつてはこの日に正月の松飾りに使う木を採りにいったり、煤払いや餅つきをしていた。今でも各地の神社やお寺ではこの日に煤払いなどの行事が行われる。また、京都の祇園では、12月13日に芸奴や舞妓が師匠の家にあいさつに行くしきたりがある。 |
|
| ◆ 大晦日(おおみそか) | |
|
一年の最終日の12月31日。年内最後の晦日(みそか=毎月の最終日)で、大晦(おおつごもり)ともいう。新しい年神様を迎えるために寝ないで待つ日とされ、早く寝ると白髪になるとの言い伝えがある。大晦日の夜のことを除夜(除夜)といい、神社では火を焚いて厄祓いの神事を行ったり、お寺では年をまたいで除夜の鐘をついたりと、さまざまな年越しの行事が各地で行われる。 |
|
| ◆ クリスマス(Christmas) | |
|
イエス・キリストの誕生を祝うキリスト教の祭り。12月24日をイブ、25日をクリスマスとして祝う。実際のイエスの誕生日は不明で、12月25日は古代の太陽信仰に由来する祭りの日ともいわれる。英語の「Christmas」の語源は、「キリスト(Christ)のミサ(mas)」。日本での最初のクリスマスは、1552年に現在の山口県周防で宣教師たちが日本人信徒を招いて行ったミサとされる。 |
|
| ◆ 忘年会(ぼうねんかい) | |
|
師走は忘年会のシーズン。一年を振り返り、酒を飲み交わす習慣の起源は鎌倉時代、武士や貴族が連歌を詠む「年忘れ」という行事に遡(さかのぼ)る。庶民が盃を交わし、一年の労をねぎらうようになったのは江戸時代から。それが明治以降、年末の習慣として定着した。「忘年会」という名が文献に初めて登場するのは、夏目漱石の『我輩は猫である』。師走の盛り場は忘年会に集う酔客で賑わう。 |
|
| ◆ 煤払い(すすはらい) | ||
|
新年を迎えるために、年末に家屋や家具の塵埃を掃き清めること。昔は朝廷や幕府で旧暦12月13日に行う年中行事の一つであった。現在では全国から信徒が集まり、毎年12月20日に豪快に行われる京都・東西本願寺の「煤払い」などのように、恒例の行事とする寺社がある。 |
||
| ◆ 雪囲い/雪吊(ゆきかこい/ゆきつり) | ||
|
家や庭木の周りを囲って吹雪や雪の圧による害を防ぐこと。庭木が雪の重みで枝を折られないように、
幹に沿って1本の支柱を立て縄を四方八方に張って枝を吊る「雪吊」は、その姿も美しく、金沢市の兼六園などでは冬の風物詩の一つである。 |
||
| ◆ 柚子湯(ゆずゆ) | ||
|
冬至に、無病息災を願って香り高い柚子の実を風呂に浮かべて入浴する。ひびやあかぎれを治し、血行促進や風の予防にもなるとされてきた。この日を境に日が長くなることから、陰が極まり再び陽にかえる日(一陽来復=いちようらいふく)とも言われる冬至に、ゆっくり湯に浸りながら春の訪れを想うのもいい。 |
||
| ◆ 柚(ゆず) | |
|
独特の香りと美しい黄色の皮が、昔から料理に欠かせない薬味として愛されてきた柚子。その芳香や、色合いがもたらす食欲増進効果に加え、風邪の予防や体内の浄化、疲労回復に効果があるとされる。「柚子は九年でなりかかり」「柚子の大馬鹿十六年(または三十年)」などの諺があるように、種子を蒔いてから収穫するまでには手間と長い時間を要する。 |
|
| ◆ 南瓜(かぼちゃ) | |
|
冬至に食べる風邪をひかないといわれているカボチャの収穫時期は夏。長期間保存がきくうえ、長く置くことでデンプンが糖分に分解されてさらに美味しくなるため、秋から冬にかけてが食べごろ。緑黄色野菜の代表で、豊富なカロチンやビタミンに加え、たんぱく質やミネラル、食物繊維など、さまざまな栄養素が豊富に含まれたバランスのよい野菜。昔は収穫の少ない冬まで保存し、この時期に食べて栄養を補っていた。 |
|
| ◆ ポインセチア(猩々木) | ||
|
クリスマスの時期に出回る観葉植物。和名は猩々木(しょうじょうぼく)というが、「猩々」とは赤ら顔で
酒を好むという中国に伝わる想像上の生き物のこと。赤い葉が酔った顔の色を思わせるところからこの和名がついた。メキシコ原産で、ポインセチアという名前は、アメリカの初代メキシコ公使であったJ・Rポインセットに由来する。12月頃に葉が赤く美しくなることから、英語では「クリスマス・フラワー」、スペイン語では「ノーチェ・ブエナ(聖夜)」と呼ばれる。 |
||
| ◆ オリオン座(おりおんざ) | ||
|
冬の夜空に瞬く星座。おうし座の日が地に位置する大きな星座で中央にみっつ星が並んでいるのが特徴。明るい星が多く、白い一等星リゲルと赤い一等星ペテルギウスを擁し、日本ではその色からそれぞれ源氏星、平家星と呼ぶ。オリオン座のペテルギウス、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンを結んでできる三角形を「冬の大三角形」という。 |
||
| ◆ 除夜の鐘(じょやのかね) | ||
|
大晦日の夜から元旦にまたがって、各地の寺院では人間の煩悩の数とされる108の鐘をつく。108と数の由来は諸説あるが。人間の感覚を司る眼(げん)、耳(に)、鼻(に)、舌(ぜつ)、身(しん)、意(い)の六根に、それぞれ好(きもちがよい)、悪(悪い)、平(何も感じない)の3種の煩悩があり、さらにこの18が浄、染(不浄)の2種に分かれ36の煩悩となり、前世・今世・来世の三つの時間軸が関って108となるといわれている。 |
||
| ◆ 林檎(りんご) | ||
|
秋から冬にかけて収穫され、冬に出回る身近な果物。日本で林檎の名前が見られるのは平安時代からで、「和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」に「利宇古宇(りうこう、りうごう」とあり、これが訛って「りんご」になったとされる。へたのある方を上に置くのが一般的だが、りんごにとっては花がついていた方(へたのない方)が頭。こちらの方を上のしておくと良く香る。 |
||
| ◆ 氷雨(ひさめ) | ||
|
本来は雷雨とともに降る雹(ひょう)や霰(あられ)のことで、夏の季節の季語となっている。氷雨がもつもう一つの語義は霙(みぞれ)。霙は雪が解けて雨まじりとなって降るもので、こちらは冬の季語。初冬や春先に見られる冷たい雨。 |
||
| ◆ 火鉢(ひばち) | ||
|
陶器製、金属製、珍しいところでは木製や石製の鉢に炭を焚いて使用する暖房器具。まきを使う囲炉
裏にくらべ煙が出ないことから、公家や武家の間で用いられていたが、次第に一般庶民にも普及した。江戸時代や明治時代にはインテリアとしても普及した。大きさや種類もさまざまで、「手炙り火鉢」と呼ばれる小ぶりのものを対で用いる火鉢や、火鉢と引き出しが一体になった「長火鉢」などがある。お湯を沸かしたり、燗をつけたり、部屋を暖めたりと、寒い日にはなにかと重宝するが、炭が燃える際に一酸化炭素が発生するのでこまめな換気が必要。 |
||
| ◆ 懐炉(かいろ) | ||
|
懐中に入れて暖をとる道具。古い時代には、火鉢で熱した石などを布でくるんだり(温石)、塩と糠を炒って布に包んで(塩温石)持ち歩いていた。江戸時代になると燃焼させながら持ち歩く灰式懐炉が普及し、大正時代にはベンジンをゆっくり酸化発熱させる白金懐炉が使われていた。いわゆる「使い捨てカイロ」が登場したのは1978(昭和53)年。昨今では電子レンジで暖めると再利用できるカイロ、充電式カイロなども出回っている。冬の必須アイテム。 |
||
| ◆ 湯たんぽ(ゆたんぽ) | ||
|
金属、ゴム、陶器の容器の中に熱湯を入れて使保温器。これで寝床や身体を温める。中国の唐の時
代からあるもので、「たんぽ」とは「湯婆」の唐音読み。「婆」とは妻のことで、すなわち妻の変わりに抱いて寝るという意味。日本に伝わったのは室町時代。足元に置いても布団全体が暖かくなり、電気ヒーターのように乾燥しない。翌朝まで暖かさが残っていて、その湯で朝の食器も洗える。 |
||
| ◆ 冬のきもの(ふゆのきもの) | ||
|
どっしりとした縮緬(ちりめん)や、紬(つむぎ)、中でも結城紬、または綸子(りんず)や緞子(どんす)、紋意匠など暖かさの感じられるものが冬らしいきものといわれています。色合い模様は、12月は押さえ気味、帯も豪華さを強調せずに単色で渋めにキメます。正月には松の内(1月7日)まで紋のあるきものを着たり、新年にふさわしい華やかなものが着られます。生地も光沢のあるもの、色も新春にふさわしいピンクやブルー、クリーム、ベージュを、模様は吉祥模様、御所解き模様、有職模様などの格調高くおめでたい模様、帯は錦(主に袋帯)、金銀糸や色糸の入った帯、豪華で上品な組み合わせは新年ならではの楽しみです。 |
||
| ◆ 綿入り半纏(わたいりはんてん) | ||
|
半纏(はんてん)そのものは庶民の仕事着、実用着として生まれたもので、いろいろな種類がある。
袖のない亀の子半纏から長半纏、皮半纏、袖なし半纏、刺子半纏、さらには変わり半纏、趣味半纏、蝙蝠半纏などなど。防寒用としてよく知られているのが、綿入り半纏。子どもを背負った上から羽織るねんねこ半纏はすっかり見られなくなった。 |
||
| ◆ 丹前(たんぜん) | ||
|
寒い時期に着る防寒用の着物。普通は厚手のウール地で、対丈(ついたけ)になっている。対丈とははしょりや揚げがなく、裾までストレートに仕立ててある着物のこと。お父さんたちのかつての定番スタイルで、最近はめったに見かけなくなってしまったが、冬場の温泉旅館には残っている。 |
||
| ◆ 褞袍(どてら) | ||
|
丹前と同じく綿が入っている防寒・寝具用の着物。男性が着る。関東では綿が入っていないものを丹前、綿入り丹前のことを褞袍と呼ぶ。関西では綿のあるなしにかかわらず丹前という。 |
||
| ◆ 腹巻(はらまき) | ||
|
鎌倉時代の簡易な鎧(よろい)である「腹当(はらあて)」から進化したものとされ、今では、お腹が冷えるのを防ぐために腹に巻く筒状の布(編み物)のことをいう。一昔までは、子どもかおじさんのものと相場が決まっていた。お腹は手や足に続き、冷えを訴えている箇所。冷えから引き起こされるさまざまな体調不良が言われている昨今、腹巻が見直され、冷え性に悩む女性の必須アイテムに。素材も柄もファッショナブルなものが流通し、さらに遠赤外線やゲルマニウム効果などをうたった機能性のある腹巻や、見えても恥ずかしくない「見せ腹巻」(主に夏用)なども出てきた。 |
||
|
◆ 寒干し(かんぼし) |
|
|
きものを長持ちさせるための手入れの一つで、寒中に衣類の湿り気をぬくために行う虫干しのこと。一週間ほど天気が続いた日に行うのが理想的。正午をはさんだ4時間程度。直射日光の当たらない、風通しのよい部屋で行う。一枚ずつ、衣紋掛けに掛け、汚れや虫食いがないかどうかチェックする。同時にタンスや引き出しも掃除し、中敷などを取り替えておくとよい。 |
|
|
◆ 御歳暮(おせいぼ) |
|
|
御歳暮とは、一年の締めくくりに時期に日頃お世話になっている人に感謝して品物を贈る習慣です。年の暮、年神様や先祖の霊にお米や餅、魚介類などを供えて祀る魂祭り(みたままつり)に由来する習俗とされています。また暮に決済をしていた商人の習慣が発展したものとも言われています。御歳暮の品物は、かつては正月のお節料理などに使う食べ物や、鮭や鰤などの「年取り魚」、蜜柑や林檎などの季節の果物が一般的でしたが、最近では日用品から食品までさまざまです。 |
|
|
◆ 年賀状(ねんがじょう) |
|
|
その由来は、新年にお世話になっている人や親戚などのお宅に伺ってあいさつをする「年始回り」の習慣とされています。とくに遠くに住んでいる人には新年のあいさつを記した書状を送る習わしがあり、これが明治以降、郵便制度の発達とともに普及したものといわれています。現在のお年玉年賀はがきが発売されたのは、1949(昭和24)年。以来新年の習慣として定着しました。本来は年が明けてから書いて送るものでしたが、いつしか元旦に届くように暮に書いて投函するのが礼儀となっています。 |
|
|
◆ 寒干し(かんぼし) |
|
|
きものを長持ちさせるための手入れの一つで、寒中に衣類の湿り気をぬくために行う虫干しのこと。一週間ほど天気が続いた日に行うのが理想的。正午をはさんだ4時間程度。直射日光の当たらない、風通しのよい部屋で行う。一枚ずつ、衣紋掛けに掛け、汚れや虫食いがないかどうかチェックする。同時にタンスや引き出しも掃除し、中敷などを取り替えておくとよい。 |
|
|
◆ 御歳暮(おせいぼ) |
|
|
御歳暮とは、一年の締めくくりに時期に日頃お世話になっている人に感謝して品物を贈る習慣です。年の暮、年神様や先祖の霊にお米や餅、魚介類などを供えて祀る魂祭り(みたままつり)に由来する習俗とされています。また暮に決済をしていた商人の習慣が発展したものとも言われています。御歳暮の品物は、かつては正月のお節料理などに使う食べ物や、鮭や鰤などの「年取り魚」、蜜柑や林檎などの季節の果物が一般的でしたが、最近では日用品から食品までさまざまです。 |
|
|
◆ 年賀状(ねんがじょう) |
|
|
その由来は、新年にお世話になっている人や親戚などのお宅に伺ってあいさつをする「年始回り」の習慣とされています。とくに遠くに住んでいる人には新年のあいさつを記した書状を送る習わしがあり、これが明治以降、郵便制度の発達とともに普及したものといわれています。現在のお年玉年賀はがきが発売されたのは、1949(昭和24)年。以来新年の習慣として定着しました。本来は年が明けてから書いて送るものでしたが、いつしか元旦に届くように暮に書いて投函するのが礼儀となっています。 |
|