3月(弥生)
| ■ |
MARCH |
≪弥生≫ |
冬篭りから目覚めた |
|
|
3 月 |
参考・引用 : 自由国民社「現代用語の基礎知識」より引用しています
| ◆ 啓蟄(けいちつ) | ||
|
啓蟄とは、土の中で縮こまっていた虫(蟄虫)が穴を開いて(啓いて)這い出てくることを意味する節気(動き出す日のこと}。新暦3月5日頃、文字通り、この頃から冬の寒さに耐えていた」動植物が春の到来を感じて活動し始める、言い換えれば、日本人が「さぁ働くぞ」と意気込み始める頃のことを言います。 |
||
| ◆ 春分(しゅんぶん) | ||
|
春分は、昼と夜の長さが同じになる日で、新暦3月21日頃。春の彼岸の中日にあたる。1948年(昭和23年)から「自然に感謝し生物をいつくしみ、春を祝福する日」だとして国民の祝日「春分の日」なった。この日から六月の夏至にかけて昼の時間が長くなる。またこの日の前後に、家族でご先祖様のお墓参りに行く習慣もあります。 |
||
| ◆ 上巳の節句(じょうしのせっく) | ||
|
上巳(じょうし/じょうみ)とは、五節句の一つ。3月3日。旧暦の3月3日桃の花が咲く季節であることから、桃の
節句とも呼ばれる。「雛祭り」の起源は京の貴族階級の子女が、天皇の御所を模した御殿や飾り付けで遊んだ平安時代の「雛あそび」が始まりとされている。やがて武家社会でも行われるようになり、江戸時代には庶民の人形遊びと節句が結び付けられ、行事となり発展して行った。その後、紙製の小さな人の形(形代)を作ってそれに穢れを移し、川や海に流して災厄を祓う祭礼になった。この風習は、現在でも「流し雛」として残っている。 |
||
| ◆ 彼岸(ひがん) | ||
|
春分の日(3月20日頃)を中日〔ちゅうにち〕として前後3日間の7日間のことを「彼岸」といいます。そして初日を「彼岸の入り」といい、最終日を「彼岸の明け」と呼んでいます。彼岸とは「河の向こう岸」を意味する仏教用語で、生死を越えた悟りの境地のこと。この時季には先祖の霊が家に帰ってくるとされ、各家庭では仏壇に牡丹餅や団子、海苔巻き、稲荷寿司などを供えて迎える。秋の彼岸も同じ。 |
||
| ◆ 社日(しゃにち) | ||
|
雑節の一つで、春分に最も近い戌の日(つちのえ)をさします。「戊」という文字には「土」という意味があるところから来ている。その日に「社」といわれる土地の神様を祀り、その年の五穀豊穣を祈る。 |
||
| ◆ お水取り(おみずとり) | ||
|
「お水取り」として知られている東大寺の修二会(しゅにえ)の本行は、かつては旧暦2月1日から15日まで行わ
れてきたが、今日では新暦の3月1日から14日までの2週間行われる。二月堂の本尊十一面観音に、練行衆と呼ばれる精進潔斎した行者がみずからの過去の罪障を懺悔し、その功徳により興隆仏法、天下泰安、万民豊楽、五穀豊穣などを祈る法要行事が主体である。修二会と呼ばれるようになったのは平安時代で、奈良時代には十一面悔過法(じゅういちめんけかほう)と呼ばれ、これが今も正式名称となっている。お水取りは12日に行われ、深夜松明に照らされながら、本尊に供える霊水を若狭井(わかさい)へ汲みに行く儀式。 |
||
| ◆ ひな祭り(ひなまつり) | ||
|
3月3日は「上巳」「桃の節句」などと言われ、厄を人形に移して祓った「流し雛」の風習がありました。それらが発展し、雛人形を飾り女の子の健やかな成長と幸せを願う現在の「雛祭り」となりました。 |
||
| ◆ 春日祭(かすがまつり) | ||
|
奈良県・春日大社のお祭り。毎年3月13日に行われる。古くは2月、11月の上申の日に行われていたため申祭り(申祭り)とも呼ばれ、宮中からの勅使が司祭してお祓いの儀を行う。春日大社は京都の加茂神社、石清水神社と並んで三勅祭の一つ。起源は9世紀まで遡ると入れる古式ゆかしいお祭りで、一般客は祭礼とお祓いの行事を拝観できる。 |
||
| ◆ 田打桜(たうちざくら) | ||
|
田植えにそなえて田んぼの土を掘る田打ち作業をする頃に咲く花のことをいう。一般的には辛夷(こぶし)のことをさすが、地域によっては糸桜、山桜などを呼ぶ地域もある。かつてはその花々が開くのを待って、農作業の適時を計った。関東では3月末から4月初めの頃。「田植え桜」「種まき桜」などとも言います。 |
||
| ◆ 流し雛(ながじびな) | ||
|
雛人形の歴史は、災厄を祓うために人形(ひとがた)を身代にして川や海に流す習慣から始まりました。
|
||
| ◆ 蕗の薹(ふきのとう) | ||
|
まだほころぶ前の冷たい土から春を告げる山菜。春の息吹を感じさせる独特の味と香で、あくも強く苦い。「春
の皿には苦味を盛れ」る春の山菜の代表格。蕾の状態で採取され、天ぷらや煮物・味噌汁・ふきのとう味噌に調理して食べられる。一般的には花が咲いた状態のふきのとうを食べる事は避けられるが、細かく刻んで油味噌に絡める「ふきのとう味噌」などには利用可能。伸びたフキノトウも葉や花を取り除き、茎の部分を軽く灰汁抜きしたものを肉や刻んだ油揚げ、糸コンニャクなどと一緒に煮付けても美味しい。 |
||
| ◆ 筍(たけのこ) | ||
|
春の訪れを実感させる味覚の一つ。モウソウチク(孟宗竹)、ハチク(淡竹)、マダケ(真竹)、ネマガリダケ(根曲竹)、と種類も多い。京阪神周辺では、京都府向日市・長岡京市や大山崎町が有名であるが、大阪市内の高級料亭では大阪府貝塚市木積(こつみ)地区生産のものも珍重されている。 また日本では、収穫事業が「竹の子掘り」と称して季節の観光行事としても親しまれている。 |
||
|
◆ 若布(わかめ) |
||
|
古くから日本人に馴染み深い海藻の一つ。「産後の肥立ちにはワカメの味噌汁がいい」とか「若返りの薬」といわれるほど、ワカメには豊富な栄養素が含まれている。ワカメは味噌汁などの汁物の具としてよく使われる。他にも酢の物、炒め物、サラダ、地域によっては天ぷら等幅広く料理される。旨み成分を多く含み、また低カロリーであることから、ダイエット食品としても適している。 ワカメに多く含まれる栄養素は、食物繊維、アルギン酸、フコイダンなどで、血中コレステロール値を下げたり、動脈硬化や心筋梗塞を防ぐなどの効果があると言われている。 |
||
|
◆ 蛤(はまぐり) |
||
|
神話や昔話に数多く登場する蛤は、遺跡からも多く出土するなど、昔からよく食されていた貝。源氏物語にも出
てくる「貝合わせ」、」ひな祭りのお供えなど日本人の生活に根ざしていた食べ物。ハマグリは元々の組合せ以外の貝殻とはぴったりかみ合わない。そこで、結婚式でハマグリの吸い物が出されることも多く、『よい伴侶にめぐり合えるように』との願掛けからひな祭りにハマグリを食べる風習がある。 |
||
| ◆ 霞/朧(かすみ/おぼろ) | |
|
暖かくなって空気中に小さな水滴や塵が浮遊し、遠くが淡くぼやけて見えること。春によく見られる自然現象で、春の季語になっている。秋に見られる同じ現象は「霧」と呼ばれ、こちらは秋の季語。夜の霞は「朧」といい、月に霞がかかった様子を「朧月夜」という。 |
|
| ◆ 春雷(しゅんらい) | |
|
春によく見られる雷。春の季語。特に立春を過ぎてから初めて鳴る雷を「初雷(はつらい)」という。また、二十四節気の啓蟄(新暦3月5日頃)の頃によく鳴ることから、春を知らせ、虫たちを目覚めさせると考えられ、「虫出しの雷」とも呼ばれた。時折、雹(ひょう)を降らせることもあるが、積乱雲による夏の雷のような激しさはない。 |
|
| ◆ 蓬(よもぎ) | ||
|
春の野草の一つ。特有の香りがあり、春につんだ新芽を茹で、おひたしや汁物の具、また草餅にして食べる。
また、天ぷらにして食べることもできる。灸に使うもぐさ(艾)は、葉を乾燥させ、裏側の綿毛を採取したものである。葉は、艾葉(がいよう)という生薬で止血作用がある。若い芽や、育ち始めた若い株は、干しておいたのちに煎じて飲むと、健胃、腹痛、下痢、貧血、冷え性などに効果がある。また、もう少し育ったものは、これも干しておき、風呂に入れると良い。腰痛を始め、痔にとても良い。 |
||
| ◆ 春一番(はるいちばん) | ||
|
春一番(はるいちばん)は、例年2月から3月の半ば、立春から春分の間に、その年に初めて吹く南寄り(東南東から西南西)の強い風。主に太平洋側で観測される。五島列島沖に出漁した猟師たちの間で呼ばれていた風の名前とされています。春一番が吹いた日は気温が上昇し、翌日は西高東低の冬型の気圧配置となり、寒さが戻ることが多い。この三寒四温を繰り返して春に近づいていく。ちなみに、春一番のあとに吹く風を、春二番、春三番といわれる。 |
||
| ◆ 春のきもの(はるのきもの) | ||
|
春は、透けない生地に裏地をつけて仕立てた「袷(あわせ)」を着ます。生地は、光沢のある絹織物の綸子(りんず)、手触りの柔らかい緞子(どんす)、生地の表面にしぼのある縮緬(ちりめん)、素材は絹ながら木綿の風合いの紬などがふさわしいとされています。 |
||
| ◆ 色目(いろめ) | ||
|
色目とは平安時代の宮中で使われた配色形式で、装束から調度品まであらゆるものに当てはめられました。
その配色は、四季折々の自然や動植物の色彩と密接に結びついています。色目には、あわせの着物の表地と裏地の布の配色を楽しむ「重ね色目」、十二単のように着物を重ね着していくときの「襲(かさね)色目」、経糸と緯糸の色の違いで玉虫色の効果を出す「織色」などがあります。 |
||
| ◆ 春の時候のあいさつ(はるのじこうのあいさつ) | |
|
卒業、入学、入社、引越しなどの年度末にあたり何かと慌しいこの季節。この時季にふさわしい時候の挨拶
は次のとおり。 |
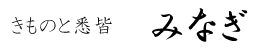









 花言葉は
花言葉は